目次
アイスランドの有給休暇と働き方
アイスランドの海洋バイオテクノロジー研究センター(以下、バイオ研究所)で働いている研究員の方と話す機会があったときに色々話した中で、有給休暇の長さが印象に残りました。今回はアイスランドの有給休暇や働き方などについて、実際に現地で働く人に聞いた話を中心に書いてみたいと思います。
バイオ研究所で働いているその研究員の方は、「自分はデンマーク人だけど、両親がレイキャビクに住むアイスランド人だから半分はアイスランド人なんだ」と言っていました。元々デンマークで働いていて、その後、アイスランドのバイオ研究所にやってきて働くようになったそうです。
「アイスランドのスーパーでは刺身をあまり見かけないが、刺身は食べないのか?」と聞くと、「生魚を食べる習慣はあまりなく、生で食べるのはサーモンくらいだ」と教えてくれたり、日本の寿司について色々聞かれたりしました。そんな雑談から、「日本に行ったことがあるよ」という話に発展し、有給休暇の話になりました。

「アイスランドでは年間5週間の有給休暇があって、そのうちの2〜3週間を利用して日本に滞在し、渋谷のスクランブル交差点で正月のカウントダウンをして、京都と大阪にも寄ったよ」とのことでした。さすが幸福度の高い国、アイスランド。会社に勤めていても、2〜3週間の有給休暇を取り、旅行に行くのは、アイスランドではごく普通のことのようです。有給休暇の日数はアイスランドの法律で決められていて、最低でも年に24日の有給休暇が約束され、勤続10年だと年に30日、といった具合に勤続年数により日数が増えます(※1)。
日本でももちろん有給休暇はあり、法律で決められています(労働基準法第39条)(※2)。会社員は勤続年数が長くなれば、年に20日程度は有給休暇を取得できますが、3週間のバカンスに行けるかというと、現実的には難しい気がします。
2~3週間のバカンスに行っても会社を続けられる、というのは、日本で働いてきた経験のある私からしてみれば、羨ましい限りです。2~3週間職場から離れられれば、かなりリフレッシュでき、休み明けにはまた仕事を頑張ろうと思えるのではないでしょうか。また、病気などで休む場合にはこれとは別に、sick leave(有給の病気休暇)が与えられます。勤務初年度でも月に2日ほどのsick leaveが与えられ、勤続年数が増えれば、sick leaveも増えます。これはアイスランドの労働者の権利です(※3)。
日本で働く多くの会社員は、私用で休む場合も、病気で休む場合も、有給休暇を使います。これはアイスランドとの大きな違いです。外資系企業の日本法人などではsick leaveを採用しているところもありますが、日本ではまだまだ主流にはなっていません。
また、よっぽどのことがない限りアイスランドでは残業はしないということです。年に1回とか本当に緊急の時だけするとのことで、慢性的な残業がはびこっている日本の労働事情を話すと、「信じられない…」と言っていました。
一方、デンマークでは…
そんなわけで有給休暇とsick leaveの日数が多く、残業が少ないアイスランドは「日本からしてみると大変羨ましい」と言ったところ、研究員の方はこう続けました。
「でもデンマークでは6週間休めたんだ…。デンマークの方がその点よかったな~」と。北欧、強い、強すぎる。そんなわけでデンマークについても色々調べました。
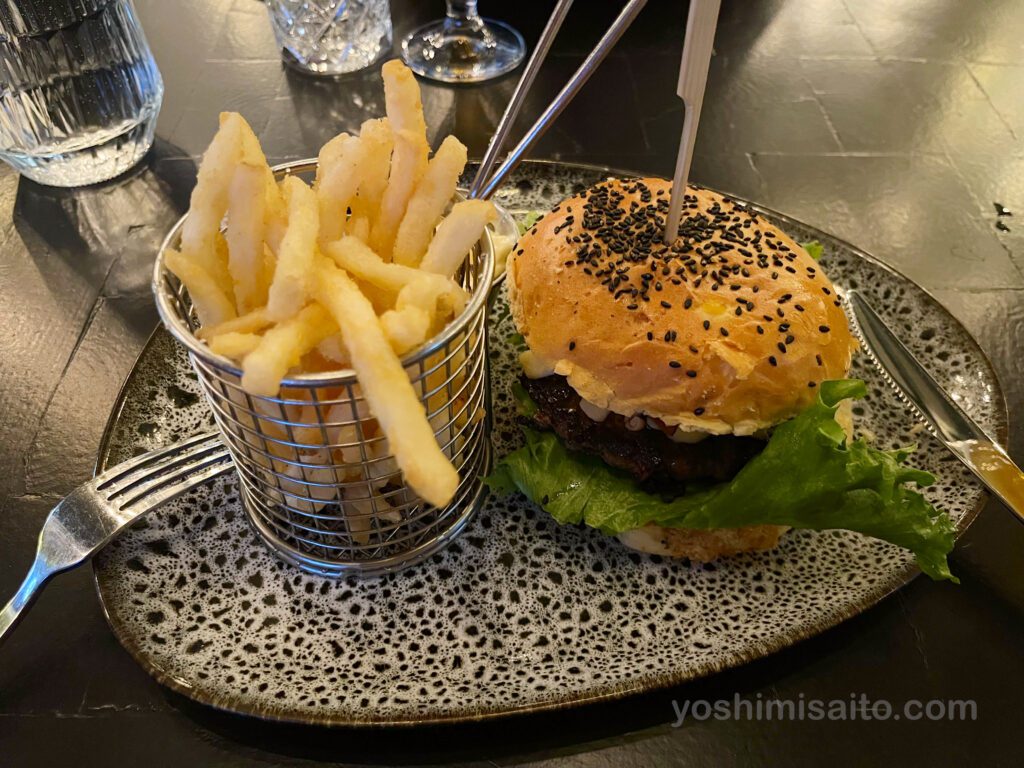
デンマークの有給休暇と働き方
有給休暇6週間、というのはその研究員の方の勤続年数や雇用契約がそうさせたのかもしれません。デンマークの法律では有給休暇は5週間と決められているようです(※4)。どちらにしろ、日本からしてみれば羨ましい話です。
デンマークでは、多くの人が夕方4時ごろには会社を退勤し、自分の時間や家族との時間を楽しむようです(※5)。4時に帰るためにとにかく集中して働き、4時になったら仕事を終え、退勤後には自分や家族の時間を持てる働き方ができたら、会社もそんなに悪い場所ではなくなるかもしれません。こうした働き方によって、従業員の幸福度は増し、仕事の生産性も上がったというデータもあるようです。
Karoshiの国、日本
「過労死」という日本語がそのまま ”Karoshi” として英文中に登場するのを見たことがあります。過労死という悲しい言葉が出来てしまった日本は、働き方においてはかなりの遅れを取っていると感じました。デンマークの働き方にも短所はいくつかあるかもしれませんが、こうした働き方も選べるようになればいいなと思いました。
労働条件について厳しいヨーロッパでは、より時短で働こうとする動きがここ数年あるようです。時短や、週休3日制などを実験的に取り入れたことにより、以前よりも売上が上がったという話を、ニュースや人づてに見聞きしました。「週休2日制で長時間働くのは前時代的」という考えが広まっているようです。
アイスランドの選挙投票率の高さ
アイスランドやデンマークなどでは、国民一人一人が政治に対して強い関心を持ち、国民がきちんと政治家を見極めているため、政治が成熟している印象を受けました。そういう基盤があるからこそ、自分たちの働き方も自分たちで積極的により良い方へと変えていくことができるのかなと思いました。残念ながら日本はまだそこに至っていないのかもしれません。
日本では「働き方改革」「女性が輝く社会」など、聞こえの良い標語だけが虚しく飛び交い、その実が伴っていないことが多いと感じます。口だけで実を伴わない政治家を選んでしまわないように、選挙について、政治について、積極的に自分事として考え、次の世代にも教えていく必要があると感じる今日この頃です。アイスランドでは選挙に行こうと言わなくても選挙に行くのが当たり前のことという認識があるようでした。
実際、2021年のアイスランドの総選挙では、有権者の80.1%が投票したということです。一番投票率の低かった20~24歳の世代ですら67.6%という投票率だったようです(※6)。
これは、小さい頃から政治に対して積極的に一人一人に考えさせてきた教育によるところが大きいのではないかと思います。
我々の日々の生活は、政治に密接に繋がっているので、政治家の良からぬ動きを注視したり、自分たちの権利について声をあげていくことが大事だなと改めて思いました。
というわけで、今回は羨ましさが募る有給休暇や働き方についてでした。
参考文献
- ※1: WORKERS’ RIGHTS – https://work.iceland.is/working/workers-rights/
- ※2: 厚生労働省 – 労働基準関係リーフレット
- ※3: Digital Iceland – Sick leave rights – https://island.is/en/sick-leave-rights
- ※4: WORK IN DENMARK – Holiday Allowance – https://www.workindenmark.dk/working-in-denmark/terms-of-employment/holiday-allowance
- ※5: Ministry of Foreign Affairs of Denmark – WORKING IN DENMARK – Work-life balance – https://denmark.dk/society-and-business/work-life-balance
- ※6: Statistics Iceland – Drop in turnout among younger voters (06. January 2022) – https://www.statice.is/publications/news-archive/elections/general-elections-to-the-althingi-25-september-2021/